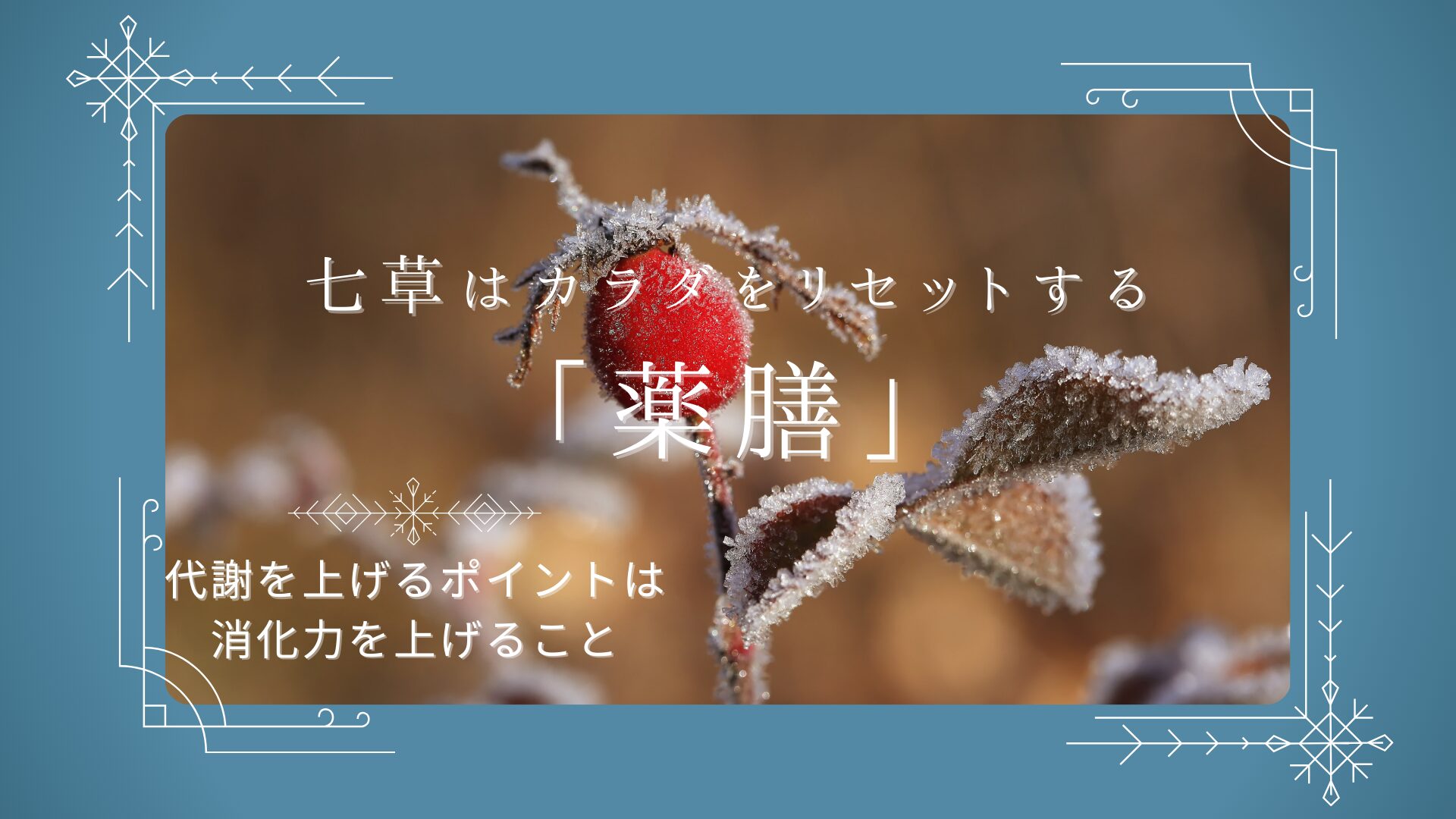お正月休みを終えて、非日常から日常に戻るころですね。
二十四節季では寒の入り「小寒」を迎えて、1年で最も寒さが厳しくなり始める時期です。
この時期には、身体が冷えやすく血流や気の巡りが滞りがちになります。
お正月で疲れた胃腸を休めるためにもぜひ和ハーブでもある「七草粥」をいただいてこれからの1年の『無病息災』を祈ってみてはいかがでしょうか。
身体をリセットして、1年の始まりに健康と幸せを祈る七草

七草粥(ななくさがゆ)は、日本の伝統的な料理で、毎年1月7日の「人日の節句」に食べられる風習があります。この七草粥には、新年の無病息災を祈る意味や、お正月の豪華な食事で疲れた胃腸を休めるという目的があります。
この日に7種類の野菜を食べて邪気を払い、健康を願いました。この習慣が日本に伝わり、平安時代には宮中行事として定着。その後、江戸時代に庶民の間にも広まり、現在の形になったのだそう。
この時期になるとスーパーでも七草セットが並びますから、ぜひ取り入れたい風習ですね。
消化力を高めてカラダをリセット
LuLuAngeで提案しているお手入れの基本のひとつに「入れるより出すこと」を大切にしています。
出すためにも「消化力」を整えることは体調を整える上でとても重要な役割を果たします。
代謝を上げるにはまず「排出」できるカラダを作ることなんです。
消化がスムーズということは、必要な栄養素をしっかり吸収し、エネルギーを効率よく得るための基本だと思っています。
消化に良いおかゆは、体調を崩しやすい冬の時期に最適な食べ物です。
七草粥を食べることで、身体をリセットしつつ、植物の力で邪気を払い新しい年の健康を願う1年の始まりに健康と幸せを祈りましょう!

セリ:ビタミンや鉄分が豊富。
ナズナ(ぺんぺん草):胃腸の調子を整える効果がある。
ゴギョウ(ハハコグサ):喉の痛みに効くとされる。
ハコベラ(ハコベ):消炎作用がある。
ホトケノザ(コオニタビラコ):整腸効果がある。
スズナ(カブ):ビタミンが豊富で消化を助ける。
スズシロ(ダイコン):消化促進作用があり、胃に優しい。
五臓に働きかけて全身のバランスを整える七草
LuLuAngeのケアでも取り入れている東洋医学。
この七草を「薬膳」の一種として捉えてみると、七草粥は冬の冷えた身体を温め、胃腸を整え、気血の流れを促進する目的で食べられると解釈できます。
薬膳とは、食材の性質や効能を利用して、身体の調子を整え、病気を予防するための料理です。
五臓と七草の関係
七草はそれぞれが五臓(肝・心・脾・肺・腎)に働きかける性質を持ち、全身のバランスを整えます。
セリ(肝・脾):血液を浄化し、解毒作用があります。肝の機能をサポート。
ナズナ(肝・腎):利尿作用があり、体内の余分な水分を排出。腎を助けます。
ゴギョウ(肺・脾):痰を取り除き、喉を潤します。肺の不調を和らげます。
ハコベラ(脾・腎):胃腸を整え、消化を助ける働きがあります。
ホトケノザ(脾):胃腸を温め、整腸作用があります。
スズナ(脾・胃):胃腸の働きを活発にし、消化を助けます。
スズシロ(肺・脾):気を巡らせ、胃腸の負担を軽減します。
七草がゆの性質
温性・平性のバランス
七草は身体を温めつつも、内臓に負担をかけない「平性」や「温性」の性質を持つものが多いです。これは、寒さで滞りやすい「気血」の流れを改善し、冷えによる不調を和らげます。
デトックス作用
正月の暴飲暴食で溜まった「湿邪」(余分な水分や老廃物)を排出する役割を果たします。
胃腸のリセット
東洋医学では、胃腸(脾・胃)は「後天の気」を生み出す源とされ、健康の要と考えられています。七草がゆの消化に優しい性質は、胃腸の負担を軽減し、生命エネルギー(気)の補充に繋がります。
陰陽のバランス調整
冬は陰のエネルギーが極まる時期で、身体が冷えやすく滞りがちです。七草がゆに含まれる葉物野菜や根菜には、陽のエネルギーを補い、全身の気血の巡りを改善する働きがあります。
七草粥の東洋医学的効能
- 解毒作用(肝のケア)
セリやナズナなど、解毒を助ける野菜が含まれているので肝の働きを促進します。 - 冷えの改善(腎のサポート)
冬は「腎」が弱りやすい時期ですが、七草が体内の温めを助け、腎の機能を補います。 - 消化促進(脾・胃の強化)
スズナやスズシロは、お正月料理で疲れた胃腸を整え、消化を助けます。 - 免疫力アップ(肺を強化)
ゴギョウやスズシロは、呼吸器系を潤し、風邪予防や免疫力アップに寄与します。
・・・・・・・・・・
七草粥は、東洋医学的には「1年の健康の基盤を整える」重要な食文化です。
胃腸を労わりつつ、体全体の気血水の巡りを改善する絶好のタイミング。
七草粥をさらに東洋医学的にアレンジして、効能を高めるのも良いかもしれませんね。
例えば…
- ショウガやネギを加えて温め効果を強化。
- 昆布や干し椎茸で出汁をとり、腎のエネルギーを補充。
- 黒ゴマやクコの実をトッピングして補腎効果をプラス。
五臓を整えることで得られる10のこと
五臓(肝・心・脾・肺・腎)を整えるということは、身体全体のバランスを保ち健康を支える基本です。
1.体調不良や病気の予防
五臓が整うと、免疫力や自然治癒力が高まり外部からのストレスや病原体に対する抵抗力が向上します。各臓器の機能がバランスよく働くことで、病気や不調のリスクを減らせます。
2.エネルギーの循環を促進
五臓は「氣血水」というエネルギーの流れを管理しているのですが、体内のエネルギー(氣)がスムーズに循環し、カラダ全体が活力に満ちて疲れにくくなります。
エネルギーが滞らず循環することで、カラダが軽く感じやすくなるんです。
3.精神的な安定
ココロの健康も五臓と密接に関連していること。
例えば、肝がうまく働いていると感情の起伏を抑えることが出来て、穏やかな気持ちを保つことが出来るようになります。
また、ココロが整うことでストレスや不安感が軽減し精神的にも安定しやすくなります。
4.消化機能の改善
脾は消化を司り、栄養の吸収を促進します。
脾が元気なら食事から栄養をしっかりと吸収し、エネルギーを供給することが出来るので体調も安定しますので、消化不良や胃腸の不快感を避けることができますね。
5.呼吸器の健康
肺は呼吸を司る臓器ですね。呼吸が整っていることで、酸素を十分に取り入れ二酸化炭素を排出する機能が向上します。肺の健康を保つことで呼吸が深くなり、全身に酸素を供給するチカラが高まります。
6.肝機能の調整
肝は「氣の流れ」を司り、感情やストレスに大きく関わっています。肝が整っていると、ストレスに強くなり怒りや不安が抑えられ、感情的なバランスを取りやすくなるんです。
7.免疫力の向上
腎は「生命力」の源とされていて、免疫系とも深く関わっています。腎が強いと、寒さや感染症に対する耐性が向上し体調を崩しにくくなります。腎を整えることは、エネルギーの基盤を強化して健康を維持するためにもとても重要なんですよ。
8.老化の予防
腎は老化に関連する臓器ともされています。腎が健康だと体力や気力が維持されて、老化を遅らせる効果があります。骨や歯、髪の健康を保つのにも重要です。
9.ホルモンバランスの調整
五臓を整えることは、ホルモンの分泌にも影響を与えます。特に肝や腎はホルモンバランスの調整に重要な役割を持っています。体内のホルモンの調和が取れて、月経周期や更年期の不調などが改善されることがあります。
10.自律神経の調整
五臓が調和して働くことで、自律神経のバランスが整いストレスへの適応力が向上します。
睡眠の質が上がったり、日々の疲労感の軽減にも五臓のケアは大切ですね。
・・・・・・・・・・
五臓を整えることは、カラダの健康だけでなくココロの安定や精神的な成長にも大きな影響を与えます。
東洋医学では、五臓を調整することで自然治癒力が高まり健康で活力のある生活を送ることができるとされていますが、日々のケアとしてはもちろんですが、季節の節目のイベントの中にもこうして体調管理や養生に役立つ知恵が詰まっていると思うと「七草」をいただく風習も大事にしていきたいな…と思えます。
ぜひ、寒くなるこれからの季節の養生に春の七草活用してみてくださいね。